映詩音ノベル〜リラク リラノの岸辺にて
1.散文詩…夜の憂鬱
2.散文詩…都市の憂鬱
3.よくある話〜りらく・りらの氏の青春
4.つかみそこねた唄
5.Mental Note〜私のメンタル・リポート
1.散文詩…夜の憂鬱
夜がながいお友達たちのために(リラク リラノの岸辺)
和の取り入れ口、はかなむ心、早春、里に詩あれば、洛陽の清明、音はただ時と争い、モザイクのように記憶のはめ絵細工を形どる。伝統という言葉に民俗という音を重ねる。人が辿った田の中の道すじ、裂布、切紙、山土、実香、おもむき、ためらい、奥ゆかしく、朴であり、春日であり、しなるかたち、やぶ深く分け入り、小高く開けた心象という照らし出された場所、至高の場所、和所、野に残された人工でない唯一の自然のありか、ふる里の言の葉。

装飾性に惑わされる。皮相な見方。見た目通り、飾られ、塗りたくられ、本心を隠そうとする。だがその中に本質なる実体が存在する?「現れは、すべてである」のではなかったか。飾られたものは、飾られてある姿がそのものの実体を表している。何が重要か?そのものとの関係性の中で、求めるものが類似を差し出そうとする。モードは体系化する。ファッションはCOMME DE である。雨に濡れた舗道、きらめく路面、偽のモード、隠そうとする声の主は、君か?
泳ぐ魚を追って、陽射しロンド小曲、蜂の蜜、流されしスケルツォに音生まれる。
花・香り・風泳ぐ坂の下の路地 明るく白く流れるわが大脳髄の闇夜。社会現象の孤立した群衆にフーガ、アメジスト・グリーンに白乳色の記憶、ざあー、ざあー、降り落ちる古典的泣く人たち、かく言う私は歴史である。孤島より舟が出ずる夏の夜の始まり。蛍火に清流照らされ、水在り、とする。
泳ぐ魚を追って、夜光虫絡まり散っていく。
赤い黒い影の中に青い人影が映る白い空虚、空洞、空気が緑で、虚空に錆色の白い赤い黒い窓。私の道道に懐かしく険しく激しく映る里の田園。思いがけなく影が消える木星の秋、茜色に流れる金星の涙。遠い、遠い、記憶なのか、夢なのか、ディスタンスだけが実在で、思い、思い、感情の希薄なのか路上の発汗、夜の影が流れ出す路地裏の青い気持ち、黄色の突風、私の気持ち、孤独の色
全部が、ドラッグして、周り1mmにひびが入り、きつくて、きつくて、きつくて喉が焼けつくように目が充血し、手の指の爪が伸びて伸びて渦を巻き、かたつむりのように渦を巻き、毛が流れている。赤い緑の風を吸うと呼吸が止まり、血を吐き出すと母に昔、教えられたが、今、その風が風呂場の下水溝の先から、吹き出してきたようだ。薬を濃厚なエスプレッソと一緒に鼻に流し込み、空海の夢を明け方のカフェ・テラスでドラッグスして、崩壊する気持ち、精神と呼ぶにはあまりにもオブスクェアーなフィールドに手探りで、しがみつく。ああ、唯一の観音ボサツ

精神の諸段階に応じて植物の名を掲げるなら、西洋植物の伝統的分類に従うことになる。バラ科であるスミレとアネモネが精神のより高次な拡がりをイマージュする媒体としてある種、異例の脱離体的精神の高みへと導くものであることは、シュタイナーの「いかにして超越的感覚の認識を得るか」の最も美しい章句のなかに取り上げられる青いバラの奇蹟と黒いスミレの不安が、人の精神をあるべき状態へ導く色彩の科学的分析に最も依存するところ多きスタイルであるのかもしれない。アネモネの精神的花言葉を求めて。
僕が雨と樹木の精霊と呼んだのは復活祭を過ぎ、空気が日中でも張り詰めるような寒気が宇宙を満たす、ある月のない夜だった。精霊は雨と樹木が婚姻し、お互いの幾分湿った気配を共有し、さらに交配するような新たな環境への適合種ともいうべきものだった。精霊はロウソクの幽かな明かりに照らし出され、色とも影とも、人の有する言葉では表現できない、未分化のかたちを現わしていた。僕は精霊に話しかけた。言葉ではなく、無意識の意識ともいうべき通底する何者かによって。
僕は一度生まれ変わった。精霊とは、Spiritであり、僕は一度Spiritと交配した。善き人として、新たな人生を与えられ、かつ常に精霊の見守りを受け、神的生活ともいうべき霊的生活を踏み出した。僕の言葉は、みな人の知るところとなり、僕の涙は、みな人の命を洗い流すこととなり、僕の真理は、宇宙の真理となった。超越的であり、前感覚的であり、象徴的であり、すべては言葉の糧となり、明けの明星のごとく光を映し出した。世界は僕の一部であり全部であり、光とともに在り、光とともに歩む。宇宙の実感とは、人生の本質とは何かという言葉が分かりかけたような気がした。
<絶望した新子は自殺して果てる>
絶望の深さとは、人によって違いのあるものなのか。死に至るまでの絶望の深さとは。
果てるとは、消滅することである。消えてなくなり、思いも気持ちも、考えも感情も、生きていた証もすべていちどきに途切れてしまうことである。しかも自分の意志を持って断ち切るものなのだ。望みある人生、望みなくとも時の継続に身をゆだね、考え悩むことなく生き続ける人の生、それも同じく人生である。様々な思いや悩みが集約される一つの決定的な言葉…絶望
虚無的な心情、憂鬱なる生、ニヒリズムの時代感情

明るい月であった。
夜半過ぎから、頭上高く、天蓋に届くような下弦の月が出現していた。
にじむような月光に明確な意志を感じる。
月に季節はない。満ち欠けの繰り返しとそれを伝える大気の流れを感じるだけだ。
とはいえ、『ねがはくは花のもとにて春死なむ その如月の望月のころ』である。
死霊の世界であれば、「おおっ!月は何故常に存在するのですか。観念が魔にとりつかれたごとくにその存在を隠しつつ…」首猛夫が過剰な言葉を費やす一例にすぎない月の月並みな表現。確かに目を離すといつの間にかその姿を隠し、存在と非在のあいだの“のっぺらぼう”のごとくに宇宙の秘密を垣間見せる。
明るい月が唯一の深夜の散歩の友であった。
記憶の連続性、一日の回想、継続する記憶、つながり
想起される一日のできごと、普通の一日、イメージと時間の連続、一日の重なり
香りの記憶とイメージの拡がり
夢と現実の交差
夢への道すじ、夢の関わり、現生
二人の自分、分裂し、非連続であり、不思議で奇妙な夢のような人生
裂け目、落下していく意識、思いだし、流され、消えていく、消去としての生
意味と無意味、点在する自分、点景としての自己存在、存在の無くなり
在りえない場所としての共同体―社会の出現―自己と他者
五月・桃と瀬、つつじが乱れ、羽子虫 我が掌中にもぞり、もぞり
煙ぶる春日の山の並みに、ひとり音振るわせ生息する
初夏は足裏に感じる大地の熱
徐々にヒートしていく血液の流れ
私の魂の糧は、青い真空の電極を過酸化マンガン水の中に通電させ、神経シナプスが、黒々に焼け溶けたときに流れ出る放電体の電磁波に口を注ぐことだ。白い霊媒を後頭部から脳髄果に包み込ませ、やがて私の魂の重みを感じ、白い泡とともに肉体に共通の不調和を感じる。輝きは増し、白光に輝き、輝き尽きて灰となり、大気中に霊体として溶け出す。アメジストの塊に電気を通し、発光体となって轟音を響かす。アッセンブリーにBleuの夜を浮遊し、濃密な青の領域に自分の神を見出す。啓示としてのBleuの痛み、TearsのGo By、苦しみの海に夜を泳ぎだし、口中に恐れを閉じ込め、夜のしじまの冷気を組み入れる。

遠くの空で聴こえるオルガンの音とラークス・タング ヒバリの声
春の風に誘われて夕べの憂いはこだまする
流れるハモンド・オルガンの赤や青、黄や緑
キャベツの葉をきざむ包丁のリズミカルな足音
雪が解けて、清流となって、野の小川にそそぐ
清明な一夜、蠱惑の夜、春の香りの流れ
桃の花のひとひらが髪に落ち
一瞬の時が凍結する
光がはじけ、大気が満ち、重力が目覚める
明け方の孤独の同一性
私とは自然の一部でありかつ自然から逸脱していく円環である
オルガンの色と私の呼笛
屈折した鏡面のような気持ちがプレスされていく
私は、真っ直ぐになる
陽春の光の喜びに満ち
そよ風に魂が洗われる
にお月、散る花、天津風、ひねもす雲間にこち吹かば、春の曙に我を忘れる。ノートに記しし、あはれの記録を夜の片隅にて雲をつかむ。それっ! ヒバリ、ウグイス、風の鳴き声、春のしじまに響く風吹奏の行方知らずとも、ウメにサクラの常春、スミレの発見にこころ洗われ、桃の香りにこころ乱れる。根より出でよ、幹より咲かせ、枝より落ちよ、やがて夜が始まり、森の結界が開く。すぎな、土筆、女郎花、野に生きる草花の領域、茜色に染まりし、夕暮れの一瞬に軽い疲労と気怠さを覚え、一日の終わりに入り込み、植物対話に身をゆだねる。菜の花日記、星降るリズム、アネモネの浮上、ポピーの揺らぎ、ゆきやなぎの形状、春のかたち。

2.散文詩―都市のスケッチ
私にとって都市の周縁は、泣き出しそうな工学的光景の一つの記憶をよみがえらせる。直線のような論理的空間の結節点として、都市交通の望郷的ノスタルジーを生の初源の状態から慌ただしく、他人事のように撹乱しつつあった、ある雨の日の午後、アスファルトの煙るさま、雨後のヨーロッパ的イマージュをいつからの記憶として、かつての両親に、そしてかつての論理学の教官に確認すればよいのか。都市の中に、音楽教室の看板を探し出し、煉瓦造りの街路灯のある街角でブロンズ制作の私的工房を探し続けた精神の暗黒は、都市でもあり、郊外でもあり、田園でもある拡散すべき地帯なのか、と人に問うたアトモスフィア 雨の午後の匂い。
A町5丁目のV字路に建つ古びた洋館で昨日、人が死んだ。この洋館は以前、病院として使用され「V字坂の白十字」と呼ばれる一種憧れのような、また一種奇妙な雰囲気を漂わせる白の洋塔形式の建物であった。何が理由であったのか、正確なことは知られていないのだが、病院として移り住んでいた前院長が失踪し、残された年老いた妻も精神に異常をきたし、そのまま廃屋となり、現在まで無人の状態が続いていたようであった。V字の先に建つためであろうか、車通りは少なく、ただ道行く人からはどちらからも目立つ場所に位置しており、街の目印となっていた。シンボルとしての白い洋館、場違いな異国の香りと歴史の淀みを残す、この建物で、過去の記憶を思い出させるように昨日、人が死んだ。
場末の映画館の裏口を抜けると、そこは青い猫が軒下に佇む、時間の停止した街であった、というのは何とも陳腐なイメージであることか。裏の扉をあけるとそこは夏への扉であるとか、鏡の国、ナルニア国、カフカ的迷宮の世界であるとか、電脳的マトリックス的日常であるとか、多層的現実、重層的構造、顕在的有意識の未来世界であるとか、神の神隠しにあった千尋のような、ランゴリアーズのような時間の停止した生腐った偽世界に入り込んでしまう、そんな不可思議な渡り廊下、虹の架け橋のような、別世界への不安と期待、それは文字通り映画の世界でしかないのか。場末の映画館すら、すでに消滅しつつある、つまらない現実。
都市の郊外、中学の時、J大学神学部にある瞑想の家とその脇に佇む黒い猫の映像が、その後の私の「世界」とのかかわりの関係の持ち方を決定的に規定してしまったのだと思う。現実と常に別にある精神的とでもいうのか、想像、あるいは観念的な世界、その二極構造(二重構造)ともいうべき精神のありように、この時から自分の姿はいつも現実と少し離れた意識として、現れるようになった。無音の世界、瞬く静寂の世界、かつ豊饒で色彩豊かなイメージとして瞑想の家と黒い猫の光景が、永遠とスピリチュアルである世界の構造を指し示す。実存としてある意識の志向性が、必ず現実では、わずかなズレとして作用してしまう、隙間として忍び込んでいく。私の日常と夢と想像。
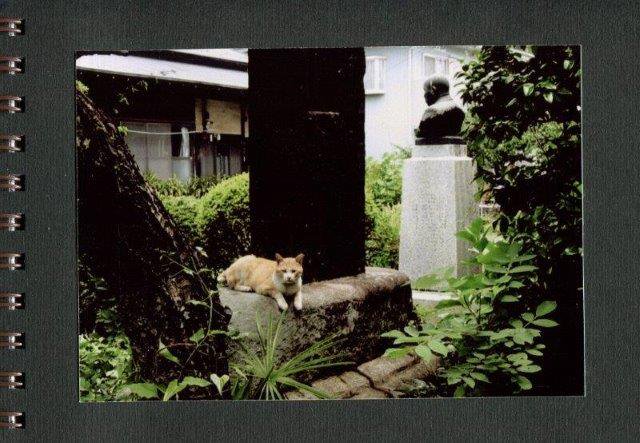
冷たい雨であった。
広尾駅から都立中央図書館へ至る道。駅周辺のわずかな通りの繁華街。普段なら横文字の看板の並ぶオープンカフェに国籍不明の客たちが昼のまどろみから楽しそうにカフェしている店先を少し行くとすぐに公園をはさんでY字路となり、登り坂に沿って歩く、暗い木立の中、大使館や洋館が並び自転車に乗る子どもたちも異国の子が多く通り過ぎる。
似たような坂の風景のようだが、どこか例えば八王子や国分寺などの景色とは違う、街の雰囲気というものがあるのか、行きかう人の印象の違いなのか、説明できない。
ただ一つ、看板や広告物がほとんど目に入らない。余計な装飾物がないのは確かだ。
冷たい雨にしっとりと落ち着いた道通りを歩きながら、考えていた。
残暑の陽がいまだ射す秋の日の午後、私は東急東横線代官山駅にいた。
代官山という言葉が匂わす都会的上質な街のイメージにそぐわない、ありきたりの私鉄沿線の一つの駅舎に過ぎない建物から早く街のただ中に飛び出したくて、この囲いから抜け出した。
そこには、心地よい秋風があった。
通行人の多くが、若い人たちで、その大半がカップルである街。街の顔があるとして労働や生活を感じさせない不思議な場所、目的があるのかないのか、ただ漂うだけの通過点として、他者には本当の姿を見せないところ。要するにデートの場所なのだろうか。
乾いた秋の日差しに海辺の避暑地を代官山に感じた。
都電荒川線の回廊
世田谷線の車窓
多摩モノレールの空中散歩
ゆりかもめの海上都市
高尾山ケーブル鉄道の吐息
東西線の地上地下ノンストップトンネルの緊張
オブジェであり、アートでもあり、日常と非日常の渡し船
とりわけローカル線で出会う風情
仙山線は山懐に入り、左沢線は田園を行く
ほっとゆだの北上線、匠の技息づく水戸線
連なる峰々、大糸線で出会う「夢」の世界
銀河ドリームラインなんて釜石線
歴史と文化と現在を結ぶ 夢の入口―改札口という扉をあけて

明日は夏だ
期待と疲労の扉
のどけき春はいつしか過ぎ、うららの春はいつ訪れたのか
マラルメと陽光
五月雨し、緑の草の匂いにむせる自然の素粒子体
しっとりとした情熱、レンブラント的光に導かれて、夜は長い
希望は万華鏡のなかの夏にあった
新宿村とは何か
新宿村管理事務所入口という案内は必要なのか
空地の彼方、建物の屋上につけられた看板は、3方向へ向けられて人に存在を訴えるが、これは何なのか
新宿から中野へ
青梅街道から大久保通りへ
紅葉山公園、その前にリイド社、さいとうプロダクション、その前に堀越学園、実践学園、その前に神田川に淀橋浄水場、そしてその前に新宿村…
電車の窓から眺めた西空にUFOを見る確率
疲れてたどり着いた冷蔵庫にスタバのラテを発見する確率
朝、ぼおっとした通勤電車で高尾を過ぎ沖電気お化け煙突の間からヨーカ堂の看板を目にする確率
ほとんど見ないテレビのCMでキョンキョンが変身したというコマーシャルに遭遇する確率
埋もれた金鉱を発見する確率を知るために書かれた統計学の本を読む人に出会う確率
外にあわてて出た時に雨が降っている確率
JR中央線で人身事故を起こした電車に乗り合わす確率
熱海、淀む海流、波打ち際の倦怠、力なき白い波頭、飛沫、陽光、海からの光、桜雨、廃屋となったホテル、かつてのグランドホテル、潮の香ではなく、すえたような人工的な生臭さ、描かれた南国風の木々、明治家庭小説である金色夜叉、歴史という強固な言葉、世界とのつながりが消えていく、自分の過去を思い出せない、自分は病的か!海は孤独する、発狂する熱海、半島の付け根
松本まで中央線各駅で近づいていく。遥かなる安曇野の地を思い浮かべて、黒光りする文化の重み、歴史の落ち着きと強固な自信を発するところ、救済と感謝、根付き、栄えるノスタルジーの残像。世界は変わらない。気分と感覚、美術館の肌触り、オランダ・ブルージュであれば淀む歴史と大気のようににじむ没落の兆しが、退廃という共通のいわば通底音が人々を侵食する。感覚の青空、雲の爽快、松本までの一駅、一駅が期待の高鳴り、思い出すところ、過去の証明。
博多あたりまでは歩いて行って、電流川を渡るところで、気息に屋台ラーメンの席に座って、明日を占う。豚骨とニンニク、発光体が裸電球に顔の脂汗を光らせながら今日の疲れをぬぐい落す。くそったれ! 場末にふさわしいネオンに流れるドブのような川、電流川に唾を吐き、吐き散らしながら、九州の北端、先端の触覚を伸ばす博多が今ある。

3. 掌編小説―よくある話〜りらく・りらの氏の青春

りらく・りらの氏の青春:国立編
[国立駅前 松本平太郎美容室窓のガラス越しに見た君は、24時53分日吉町駄菓子屋の前で待っている] (唐十郎:謎の引越少女)
映画「Shall We ダンス」ではないが、仕事を終え帰宅途中の疲れたサラリーマンが、ふと見上げた窓から姿を現した女性に恋心を抱くというのは、よくある話だ。しかし、同じく残業疲れの公務員が帰り道、何気なく目にしたビルの2階のボクシング・ジムで汗を流す若者に惚れ惚れと見とれてしまうというの
は、よくはない話だろうか。これがよく見かける新興宗教や合気道の道場だと同じ汗でもやけに胡散臭さや男臭さを感じたりしてしまうのだが、ボクシングは何故かストイックなものを感じてしまう。最近やけに目立つガラス張りの美容室には、そういった精神的なものは、もちろん関係ないのだが、国立駅前ビルの2階にある美容室は、実は前のビルに遮られて中がほとんど見えないのであって、逆に空中庭園があるのではないかという勝手なイメージをかきたてられてしまうのである。
りらく・りらの氏の青春:番外編
よくある話だが、20歳代の終わりころ付き合っていた彼女がいわゆるブラコン(=ブラック・コンテンポラリー)が好きで、話を合わせようと私も密かにではあるが、この手の音楽を聴くように努めていた。ROCKが好きだった私に合わせてくれたのだろう「シャーディーって、いいわね。Smooth Operatorをいつも聴いてるの」と言われれば、あわててレコードを買いに行ったり、当時しきりにブラコンを流していたFM番組‘クロスオーバー・イレブンをせっせとカセットに録音したりしていた。Stevie Wonderが音楽を担当しているからという理由で一緒に観に行ったGene Wilder主演の「Women in Red」も、せつない恋愛コメディだったが、「つまらないね」の一言で終わってしまった。その後だんだん会う回数が減り、お決まりの「いいお友達でいましょう」状態からいつの間にか「いなくてもいい人」になったようで、熱に憑かれたように録音したテープが一本ずつ減っていくにつれて、好きだった気持ちがどこかへ蒸発していったような感じがした。あの頃、街に出ればどこにでも流れていたFreddie Jacksonの「Rock Me Tonight」を今、一人で聴くと、漂うようなリズムに体を揺らしていたあの時の彼女の魂の安らぎが伝わってくるような気がしてならない。

りらく・りらの氏の青春:番外編―その2
[「タルキニアに立ち寄ってもいいわね」とサラは言った。「その前にビター・カンパーリを一杯飲みたいものだわ」](マグリット・デュラス)
「アッ…」 そのピアノ曲の最初の音が店内のスピーカーから出た時、彼女と私は同時に音の出る方向に顔を向けていた。そこは池袋西武美術館にあるアールヴィヴァンのレコード売り場で、当時ニューウェーブやプログレッシブ系ロックから現代音楽まで比較的安く手に入るのと時代の先端の音が聴ける場所として、よく通った場所だった。その曲はJohn Cageという作曲家の“A Valentine out of Season”で、ブリペアード・ピアノを使ってインドネシアのガムラン音楽のような響きを作り出したもので、彼女との出会いはこの”季節はずれのバレンタイン“という曲から始まった。彼女は私立の音大のピアノ科を出て、特に職に就くでもなく退屈しのぎにアテネフランセでフランス語の勉強をしているという、いわゆる暇を持て余したお嬢様で、ヌーヴォー・ロマンやゴダール以降のフランス映画を好み、よくアテネフランセへ映画を観に行っていた私とは話が合い、お茶の水から銀座に出てSonyビルでケーキを食べるというのがお決まりのコースとなった。その後、何度か会ううちに彼女の音大時代の友達を紹介され、その子が持っているという軽井沢の別荘に誘われることがあった。当時、駅前からゴルフ場以外何もない大通りを真っ直ぐに南に下った別荘地にあったその建物は、男女3人ずつのグループには十分な大きさで、昼間は旧軽の人混みを避けて、別荘の住人が憩うというレイクニュータウンでボートに乗ったり、夜は手製の料理に父親自慢のアルコール類でパーティーをしたりしてちょっとしたヴァカンスを楽しませてもらった。よくある話だが、その場では何事もなく、3回ほど重ねた別荘住まいの『愛を模索する主人公、彼らは常に死を呼び込みながら生きている。夏の地中海を舞台に、愛の不毛と虚無を描く』という境地にまでは至らなかった。
りらく・りらの氏の青春:京都編
[清水へ祇園をよぎる桜月夜こよい逢う人みなうつくしき]
ルイ・マル監督の『死刑台のエレベーター』は、完全犯罪を企てた男が偶然エレベーターに閉じ込められてしまったことから計画が狂いだし、破滅に至るという映画だが、最後のところで犯行の動機が、フィルムを現像して現像液の中から印画紙の上に浮かび上がってくるシーンでは、さすがに背筋をスッーと冷たいものが走り抜けるような気がしてしまう。[フィルムに写し撮られてしまった人生]…そのようなものがあるとすれば、私も不思議な経験をしたことがある。就職して5年目ころ、付き合っていた彼女は写真の勉強をしていて、今でこそ珍しくないがニコンのFシリーズのマニュアル機を首から下げ、風を切って街中を歩くような娘だった。特に植物写真が好きで、中でも蓮の花に魅せられていた。別に仏教徒ではないが、暑い夏の盛りにすくっと天に向かって咲くその姿と何より花の質感が写真に馴染むといって、近くでは上野不忍池から神奈川三渓園など蓮の花の名所を一緒に廻ったものだった。「やっぱり京都に行こうよ」と言い出した時はさすがにためらったが、昔の街並みや建物の写真をテーマにしていた私にとっても京都は魅力であって、「夏の京都もいいか」と一緒に行くことに同意してしまった。京都の蓮の名所といえば、浄瑠璃寺の蓮池が有名だが、奈良に近い南山城にあるため交通が不便なので、もっと京都らしい散策を楽しみながら行けるところとして嵐山から嵯峨野に廻る天龍寺と大覚寺の大沢池コースを選んだ。そして暑い中、ひと通り写真を撮り終えたあと、せっかく京都に来たんだからと二人ともRockやBluesが好きなこともあって、ライブハウス下京区富小路仏光寺下ル『磔磔(たくたく)』と上京区大宮通下立売下ル『拾得(じっとく)』ハシゴして、暑い京都の夏の夜をさらに汗を流して過ごした。不思議な経験というのはそのあとのことで、深夜一息入れようと二人で入った『BLUE NOTE』という店で、頼んだカクテル「ドライ=マティーニ」のグラスを傾けながら底に沈んだオリーブをボーッと見ていると店のママが「何か見えますか?」と話しかけてきた。ママは自分は星占いに凝っていて人の未来が見えるといい、私たち二人の星座を聞きながら「あなたたちは恋人どうしですか。でも将来結婚することはないように映っていますよ。嘘だと思ったら、あなたの首にかけているそのカメラ、東京に帰ったらフィルムを現像してごらんなさい」と言って、占いを終えたようだった。もちろんその場では、面白半分に聞いて、「結婚?」なんて言いながら二人で笑っていたのだが、東京へ帰ってその後、彼女から「変な写真が1枚写っていた」という電話がかかってきたのだ。人物は撮らないのに最後に1枚、ぼんやりと人が二人並んでいて、一人は感じからして自分、だと思うが、横にいる男の人はあなたとは違うような感じがするというのだ。さすがに気味が悪くて、早速彼女と会ってその写真を見せてもらったのだが、彼女の言う通り、そのぼんやりとした写真の彼方から微笑んでいる男は私ではなく、二人の知らない人だった。その後、よくある話だが、ママの予言通り彼女と結婚することはなく、また、彼女が結婚した相手がその写真に写っていた男だったのか、確かめてはいない。
りらく・りらの氏の青春:番外編―その3
[このブルーの中で私の一番好きな、気持ちに合った色がラピスラズリのブルーなのです]
ルイ・マル監督の『死刑台のエレベーター』は、ラストで印画紙に浮かび上がった犯行の動機である男女の関係が、あまりにも生の喜びにあふれ充実した姿であるのに対して、物語の大半を占める現実の空虚な生を表すのにMILES DAVISの乾いた音楽が効果的に使われているのだが、同じくマイルスのアルバムに『Kind of Blue』という印象的なタイトルの1枚がある。これはBlueな気分をスケッチしたといわれるもので、色彩の青のイメージとは違うように言われているのだが、その中に『Blue in Green』というまさしく色のこととしか思えない曲がある。この曲名をみて思い出すのが、美術学校に通っていた時の彼女のことだ。「どこを見ても自然は緑だらけ、当然のような緑の横溢をみると耐え難くて、気が狂いそうになるの」と言って、彼女は緑を一切使わず、すべて自然の草や木々を青で描いていた。その彼女が好んで使っていた青がこの“ラピスラズリ”のブルーだった。ラピスはラテン語で石を、ラズリはペルシア語で紺碧色を表す宝石で、日本では古くは瑠璃と呼ばれていたという。もちろん宝石として珍重されていて、聖書に出てくるサファイアも実はラピスラズリであったとされている。これを粉末にしたものが顔料として用いられているのだが、濃青色の顔料には藍銅鉱(アズライト)というものもあり、これを使うと次第に孔雀色に変化して緑色に変色していくそうで、ルネッサンス期の絵画にその例があるといわれている。そういえば、昔から青色に憑かれた画家というのは数多く存在したわけで、フェルメールの青から近年ではマックスフィールド・パリッシュのペルシャンブルーとかイヴ・クラインのインターナショナル・クライン・ブルーなどがあり、さらにデレク・ジャーマン監督の『BLUE』は最初から最後まで青一色の映画である。彼女はこの顔料の材料を日本では手に入らないといって、イタリアから取り寄せていたのだが、霊的に非常に強いパワーを持つとされるラピスラズリの力のせいか、作品を作り上げるときは幾晩も徹夜して一気に描きあげていたものだった。ブルーな気持ちはやがて人を狂気に導くといわれるが、青に取り憑かれた彼女に対して、私は青ざめるしかなく、憧れのイタリアへ絵を学びに彼女は飛び立って行ったが、その後の消息は聞いていない。

りらく・りらの氏の青春:品川編
[私は広い海に出るわ とても青い海は遠いわ…](五つの赤い風船)
「東京で穴場の美術館といえばやっぱり原美術館でしょう」とただ一度だけ行っただけなのに、さも知ったふりして話したら「私、すぐ近くに住んでいるの」と言われたときは、さすがにしまったと思った。品川駅から歩いて10分、御殿山ヒルズの庭園内にある原美術館は1938年に建てられた洋館で、館内を歩くと木の床のきしむ音が時代を感じさせる美術館だ。彼女は京浜急行線北品川駅を降りた旧の東海道である北品川商店街の魚屋の娘だった。よくある話だが、就職して6年目のそのころ、私はそろそろ仕事の先が見えてきて、やっぱりつまらないから辞めようか漠然と考え始めていた。辞めて何をするのか、本当にやりたいのは本の編集やデザイン関係の仕事だった。全く夢のような話に友人は絶対辞めないほうがいい、と一言で答えてくれた。でもやり直すなら30になる前の今しかない。心の中でこの考えが膨らむにつれて、何かしないといけないという気持ちが強迫観念のように広がっていた頃だった。都内のデザイン学校に通い始めて彼女に出会ったのだ。色白でオカッパのいかにも美術系という顔立ちの彼女を初めて見かけた時から気になっていたのだが、たまたま選択科目でとった版画のクラスで一緒だったことから話をするようになった。先生の個展が銀座で開かれるときは一緒に出掛け、日動や南天子画廊などをハシゴしたあと「ランチタイムは安いの」といって登亭のうな重を食べたりしたものだった。初めて北品川の彼女の家に行ったのは、「料理教室でローストビーフの作り方を習ったの、今度食べに来ない?」と誘われた時だ。品川のイメージからは想像できない庶民的な下町商店街にある彼女の実家にその後もどういうわけか数回おじゃました。実家から商店街を抜けてゼームス坂通りを経て大井町に出たり、ゲートシティ大崎で待ち合わせたりしたこともあった。ゲートシティプラザ・アトリウムで“もとまちユニオン”のアクア・スパークを飲みながら、流れているBoz Scaggsの『We’re All Alone』を聴いていると「そうだ海に近いんだ」ということに突然気が付くこともあった。穏やかさの中に、何か永遠の美というものの存在を知っているような彼女の性格は、下町っこというよりむしろ海の近くで育ったというところからくるのではないだろうか。そんなことを勝手に想像しながら、やっぱり今の仕事を続けようと思い直してデザイン学校を辞め、都内に出ることも遠のきつつなった2年後には彼女との付き合いもなくなってしまった。
※原美術館は現代作家の作品紹介を主な活動目的としているのだが、2階に個室があって
そこに我が草間彌生の作品が展示されている。‘自己消滅’と題されたその作品は精神を
病んだ草間が、自らの肉体と戦うことによってかろうじて精神をつなぎとめていたと
いう、ありふれた日常品に粘土のようなねじれた装飾を狂気に憑かれたように黄色で
塗りたくったものであり、この部屋でいっときを過ごせるだけで訪れる価値がある。
※『We’re All Alone』というのは『私たちは皆一人ぼっちだ』と思っていたのだが、『二
人だけ』という意味であることに今更ながら教えられた。
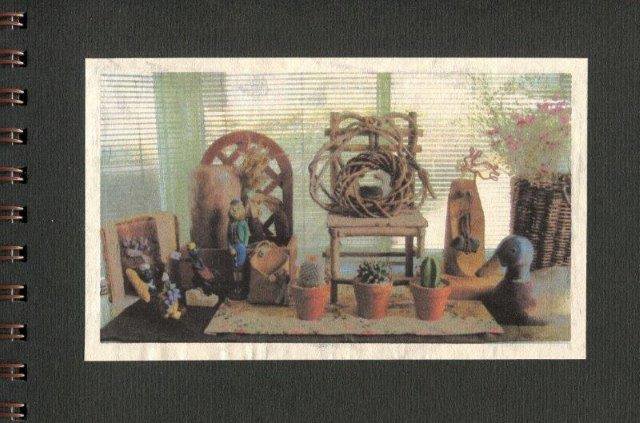
りらく・りらの氏の青春:国分寺編
[ひしゃげた感情こそがブルースの心であることをブライアンは知っていた]
黒人ブルースの‘こ’の字も知らない奴に、いきなり「ブルース・バンドやろう」と言い出されても、よく言うよ、とバカにしていたのだが、「いいヴォーカルの娘なんだ。今度紹介するよ」と言われれば幾分期待しないわけでもなかった。国分寺のSOUND IN ALEXANDERで彼女に初めて会ったのは、日が暮れた後もまだ熱気が淀んでいるような夏の仕事帰り。彼女は同じ会社の営業所に勤めていたが知らない娘だった。「浅川マキの“ハスリン ダン”なら歌えるかもね」。その頃、憂歌団がメジャーになって日本語のブルースも少しは聴けるかなと思い、聴き始めた中に浅川マキの“Blue Spirit Blues”が入っていた。おかげでちょっと大げさに言えば生まれて初めて女の子とブルースの話をするという機会を得たことになった。彼女は学生時代、演劇をやっていたというだけに声量があり、BILLIE HOLIDAYのアップテンポの曲が好きで、本当はジャズヴォーカルをやりたいと言っていたが、今思えばちょっと変わっていたのかもしれない。国分寺南口のアンティックがらくた通り、別名”夜更かし通り“に並ぶドラゴン・ママ、ぶりきかん、古着屋に我乱具多屋に生活舎、BAT MANにPINK FLAMINGOなどを冷かしながらハシゴしたあと、ほんやら洞でカレーを食べるかと思えば、国立公民館での画期的な催しアマチュア・ブルースバンド大会で飛び入り出演して驚かせたり、国立スカラ座で仕事の後最終回にいつも最前席でポップコーン片手に恋愛映画を見入っていた彼女。そんな彼女を見ていると”ハスリン・ダン“もやっぱり明るい曲だ、浅川マキだって陽性の人のように思えてきた。黒い男の人が歌うブルースは、どんなに明るい曲でも、どんなに力強くたくましい曲であっても負の影を感じてしまう。男と女の違いと言ってしまえばそれまでだが、ブライアンの弾くスライドギターの音を聴いてしまったココロの在りようで、”ハスリン・ダン“のアコースティックギターを真似しようともがいているのが、何か空しく感じられて仕方がなくなってしまっていた。その後、彼女を紹介してくれたベース弾きが立川から引越してしまい、彼女も私のぶったるブルース漬けに呆れ果てたのか、やがて遠のいていってしまい、私たちの[国分寺GOLDENAGE]も終わってしまった。

りらく・りらの氏の青春:番外編―その4
[Oh! BLIZZARD 閉ざせ二人を 流れる距離と時間を消して]
ホイチョイ・プロダクションはやっぱり天才だ、と思わせたのは映画『私をスキーに連れてって』が企画された時だが、続いて第2作の『彼女が水着にきがえたら』は期待外れでつまらなかった。同じようなものじゃないの、といわれればそうかもしれないし、三上博史と織田裕二の違いじゃないのという意見はかなり近い線のような気がする。でもやっぱりそれは、スキーとマリンスポーツの違いであるといいたい。『愛は疾走感覚の中で成就する』といわれるようにスキーにあるストイックなスピード感が、海にはないのだ。『タイタニック』の有名な舳先のシーンでのスピード感覚はもちろん、『ポンヌフの恋人』のセーヌ川花火をバックにした水上スキーのシーンは狂わんばかりに強烈だ。『彼女が水着に〜』でもジェットスキーやモーターボートチェイスなど似たような場面はあるのだが、愛とは関係のないシチュエーションであり、まして水中はスローモーションある。スキーのスピード感覚は、まだ車を持っていなかったその頃の私にとって唯一味わえる疾走感だった。「彼ったら関越をカレラで200キロ出すんだもの」と医者の友達とのドライブを楽しそうに話す彼女の言葉に実感がなかった。200キロという速度がどれくらいのものであるのか体感として意識できないのだ。しかし、スキーのスピードが時速何キロであるのかは分からないが、風と一体となりながら、意識が覚醒していく感覚は確かにあった。このスピードに追い付くために愛が必要なのか、二人の愛を捉えるためにスピードが必要なのか。流れる距離と時間を消すのは、吹雪のような荒々しい愛なのかもしれない。彼女と二人で苗場リーゼンスラロームを直滑降で滑り抜けた一体感と法悦感が、雪のまぶしさの記憶とともに今なお残っている。
文化と不思議は すぐそこに あなたの目の前 あなたの未来にある

4.つかみそこねた歌
飛び出しては危ない
踏み出しては覚束ない
ころんでは立ち上がれない
手をはさんでは痛い
目を閉じては帰れない
駆け込んでは戻れない
つまずいては振り向かない
死にそうになっては息を吸えない
首を吊りそうになっては足がつかない
焼けそうになっては逃げるしかない
気が狂いそうになっては笑うしかない
うつむいている人たちを見る
あえいでいる人たちがいた
目をそらす人との間合い
体を背ける人との呼吸
雲った瞳 かすんだ眼光
意気消沈 とまどう 戸惑う
ネガティブ 後ずさり うなだれ 目を落とす 肩を垂れる
顔を覆う 口を閉ざす 息ができない 不整息
呼吸に意識が集中してしまう
呼吸に神経が絡みついてしまう
明け方が怖い 寝ることが怖い 意識がなくなったまま戻ってこなかったらどうしようと考えると眠ることが怖い
外れることもあれば、ずれることもある
踏み外すこともあれば、つかみ損ねることもある
つまずくこともあれば、気まずいときもある
思い込むこと 気迷うこと
的を外すこと トンチンカン
要領を得ず 言い間違い
明らかにすべきは、精神の苦しみの度合い
出てこない 出口なし
はずれた音程 狂った和音
不安にする線描 迷い込む色彩
崩れることもあれば、ずれることもある迷路 壁 落とし穴 吊り天井 言葉にならないめまい
白い恐怖 白昼夢 蒼白

コンクリートと鉄と木材
コンニャクとアロエと繊維
太陽と光と海
一瞬と清明と永遠
植え込みと垣根と土塀
コラーゲンとポリフェノールとカテキン
タリーズとモカローストとジャズ
豆乳と黄な粉と黒豆
梅と実と茶
声と息と歌
コンニャクとアロエと繊維
「たはむれに母を背負ひて そのあまり軽きに泣きて 三歩あゆまず」
これは、短歌である。啄木の歌である。有名なあまりに有名な悲しい歌である。「秋風のこころよさに」と題された歌集にある<かなしみ>という言葉の多さよ。“かなしきは秋風ぞかし””青に透く かなしみの玉に枕して“”あめつちに わが悲しみと月光と”
そして「悲しき玩具」である。
啄木24歳にして死す。
三行書きの歌 貧困と孤独にあえぐ わが啄木讃
5.Mental Note〜私のメンタル・リポート
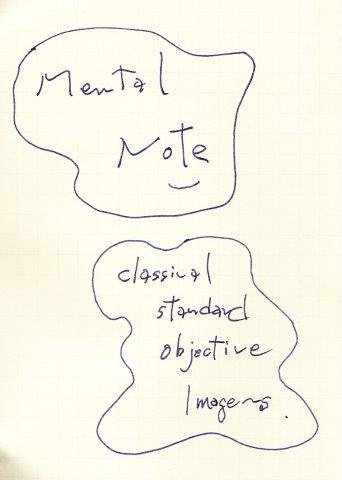
記憶の連続性 一日の回想 継続する記憶 一日のつながり
想起される一日のできごと 普通の一日 イメージと時間の連続 一日の重なり
香りの記憶とイメージの拡がり
夢と現実の交わり 夢へのみちすじ 夢へのかかわり 現生
二人の自分 分裂し非連続であり不思議で奇妙な人生のあらわれ
裂け目 落下していく意識 思い出し、流され、消えていく消去としての人生
意味と無意味 点在する自分 点景としての自己存在
存在の無くなり 在りえない場所としての共同性―社会
自己と他者 他者の出現―社会 社会の発見
神戸―カルカッターチューリッヒ 3つの都市で進行する物語
決して、人の恋愛を扱うものではなく、家族のことでも、若者の物語でもなく、要するに人の生きることをテーマ=対象とするものでない。人の生きることをテーマとすることなく、人の考えること、精神のこと、自然の在りようのこと、要するに理学的?物的?構造的?な人間の現れを世界のこととして小説にすること。
精神世界の教養小説 チューリッヒに始まり、カルカッタを経て、神戸で成就する物語とは?
精神は振り返る。
そこに何も、だれもいないことを確かめるために。
白昼の精神は誘惑され、自身の姿を見失う。
形を成さないもの、あいまいな空気 満ちてくる波のようなもの
名付けえない線、容積とあふれる状態
カラスの黒と闇の黒、漆黒 把握できない黒の拡がり
白昼と白光、乱反射する意識 もうろう、物体と記憶
明け方の余情 振り返る精神
午後2時の列車に乗る。
どこへ行くのか?人を怠惰にさせるぬくもりと軽い疲労を連れて、私はまばらな人々の群れと一緒に東京行の電車に乗る。平面構成に不可逆の光脈を見出し、ドルセバウアーの一般理論を再構築させる検証に偶然にも立ち会わせてくれたN美術館所蔵のインスターション「海辺P―3」に一種のとまどいを感じて、眼の記憶をたどる。あれは、3両目B列7の座標上にある中央特快東京行であった。
梅香る大気の果て、空のゆくえに頭を向ければ、しみいる青の拡がりのパレットに白雪を散らしたるらし福香の想い、懐かしき香りの記憶にわずかに目覚めれば、幼少の頃のときめき、野や里の静けさ、ひとりあった家路のさみしさ、隣に咲く沈丁花の錯乱、庭梅にとまりたるウグイスの朝声、はるか天空にまで時を想い計る子どもの頃の記憶 名にしあらば、はや50年、隔世の想いがホホを伝わり、だれに語るでもなくだれと思い合うこともな









